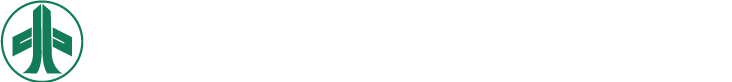2019年度第2回中同協経営労働委員会 参加報告(経営労働副委員長)
日時:1月29・30日(水・木)
会場:TKP新橋カンファレンスセンター
第1部 報告・協議・審議事項
(林経営労働委員長より問題提起)
(1)企業づくりにおける「総合実践を阻む3つの壁」
1.自らの経営課題を「労使見解」の見地から解決する姿勢はあるか
2.同友会活動と自社経営を「不離一体」にする姿勢があるか
3.責任を持って「社員を信頼する覚悟」を持っているか
(2)「ビジネスと人権指導原則」 国別行動計画(外務省)に関連して
①中小企業分野では中同協のみ委員を作業部会に出しており、経済分野の経団連と並んで討議している。
②「労使見解」が世界的な視野で誇れる内容と評価されたこととも共通して、「労使見解」を実践する同友会への外部評価が高いことに確信を持つ必要がある。
(3)経営指針成文化・実践運動について
①経営指針成文化の過程で「労使見解」を組み込み、「実践の手引き」「企業変革PG」、「労使見解」を連動して学びを深める
➁入会会員が「経営指針」を作成することを保障できる規模と内容。
➂地域課題を経営課題としてとらえ、経営指針に位置付ける視点を大切にする。
(4)企業変革支援プログラムの普及と改訂
①支部例会や行事企画でどのように位置づけるかが重要。
(5)5万名運動に向けて「増強する経営労働委員会」になろう
①外向きに発信していくことが求められる
②経営労働委員会こそが、同友会の質と量を発展させるべく尽力することが求められる
第2部 経営指針成文化・実践運動の発展を目指して(事例報告・グループ討議)
・事例報告:奈良同友会
奈良の10年間の経営指針成文化の変遷
・課題・対策が報告された
(報告内容)
①理事から一般会員に至るまで経営指針成文化に取り組んだこと
②青年部の受講者も多い
③受講者は作成した翌年以降もアドバイザーとして携わっている
④継続指針成文化に取り組んでいる
⑤県外からも講師を要請して質の向上を図っている
⑥会員の成熟が進み、カリキュラムごとに講師を分担して更なる躍進につなげている
(考察)
経営指針成文化はもとより、経営指針を社員と共有していく手法として、「労使見解」を重視されていた。経営指針を実践し現実的な成果に結びつける役割を「労使見解」が担うと確信した。
第3部 学習・意見交換と協議事項
講師 国際労働機関IⅬO 田中 竜介氏
(1)持続可能性
①現状の社会システムを未来へ繋げるサステナビリティの実現
➁SDGsの目標8「ディーセントワークと経済成長」は重要課題である
(2)働き方改革
①労働時間法制の見直し及び労使対話
②ライフワークバランスと差別をしないことの価値
③会社全体での議論+サプライチェーンにおける議論
④情報共有とピア・ラーニングによる底上げ
(3)最低賃金
①地域格差をどうやって埋めていくのか
②業種ごとにも細かく対応策をつくり施策で不平等にならないように留意
(4)ディスカッション
(考察)
賃金より休み方を大切にする傾向なので柔軟に対応する必要がある一方で、経営指針をきちんと示し、賃金上昇の担保をとることで、安定的な基盤を持続させ経営者の責任を果たしていく必要があると感じた。
(総括)
経営指針成文化の重要性については言うまでもないが、経営指針を実現するために「労使見解」というものがあるということに感銘を受けた。経営指針成文化で本当に業績向上ができるのか、社員の反発にどう対処していくのかという課題に明確な答えを見出すことができた。
一方で世界の潮流を受けての日本の方針を捉えることで、新たなビジネスモデルの創出と、人間らしく働きやすい環境整備を率先して実現する姿勢を示すことこそ、世界的な評価につながり政府からも頼りにされる中小企業家団体として、確固たる立場を確立していくことで、中小企業家同友会の躍進に繋がるのではないかと考える。
文責 県経営労働副委員長 平野 大介