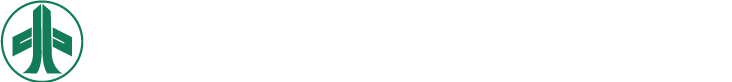【経営フォーラム in 平戸】第1分科会 経営環境
日時:11月29日(金) 13:00〜20:00
会場:平戸文化センター
テーマ:中小企業の成長と発展 ウィズコロナ、アフターコロナをどう考えるか
報告者:長崎県立大学経営学部経営学科 准教授 田代 智治氏
室長 森 誠治

田代氏は、過去に起業し、実際に企業の長として企業経営に携わり、経営の実践を通してその厳しさに触れるという研究者としては少々珍しい経験を持つそうです。
日本の企業総数における中小企業の割合はおよそ99%、社員数における割合はおよそ70%。地域、地方強いては日本の活況となるためには中小企業が元気にならなければならないとよく言われます。
田代氏は、中小企業が真に「活力ある主体」と変貌するためにはどうすればよいのかということを追求し、数多くの中小企業トップとのヒアリングにて成長発展している中小企業にはいくつかの特徴がみられると言われました。
また、中小企業が発展していくために、地元とのつながりが不可欠であり、行政、多種の企業等で強固なコミュニティ基盤をつくり上げることが肝要だということも言われました。つながりが強固で濃密ならば必然的に、地域やコミュニティに参加する企業への支援、協力が自発的に発生し、地域の活性化につながっていくという。そんなコミュニティが実際に存在する、波佐見町の朝飯会がまさしくその典型だそうです。「同友会」もその典型ではないかと感じました。
このコミュニティには、田代氏がキーワードとして挙げた「義理・人情・なにわ節」が、色濃く存在しているのだろうと思われました。そして、このようなコミュニティには、年齢や役職など関係なく、相手を認め、自分のことを認めてもらって対等な立場に立って、本気で向かいあう「対峙力」が存在するのだろうとも感じられました。ある意味「同友会」もその典型ではないかと感じました。
今回の報告を聴いて、中小企業がいかに地域に必要不可欠で、1つの企業だけで地域を活気あふれる地域と変貌させるのは不可能であり、束になって全員野球で地域の活性化に向き合うことが大事だと考えさせられました。
田代先生、貴重な報告、本当にありがとうございました。